「電気の授業がつまらない」「公式ばかりで意味がわからない」
そんなふうに感じているあなたへ。
実は僕も、かつてはまったく同じ気持ちでした。
高校時代、電気回路の授業はまるで呪文。オームの法則なんて頭に入らないし、なぜそれを学ぶのかもピンときませんでした。
そんな僕が今では、国立大の電気系大学院を卒業し、日経大手メーカーで電気開発の研究職として働いています。
この記事では、僕が「電気が楽しくなった瞬間」と、それに至るまでの3つの工夫を紹介します。
① スマホや家電の仕組みとつながったとき
スマホや家電など、身の回りにある「電気製品の仕組み」を知ると、電気はぐっと楽しくなります。
数式だけで終わらせず、現実とつなげて考えると、理解も定着も早くなります。
僕はスマホのバッテリーやコントローラの仕組みを調べたことをきっかけに、電気が身近でおもしろいものに変わりました。
「これは何で動いているんだろう?」という好奇心が、学びの入口になります。
② 電子工作で「動いた!」という実感が得られたとき
電子工作を通じて、自分の手で「電気をコントロールする感覚」を得ると、楽しくてやめられなくなります。
電気を“操作できる”という感覚が、自分の世界を広げてくれます。
僕がハマったのはLED点灯キットでした。ボタンを押して光がついた瞬間、「自分で動かせた!」という感動がありました。
そこから回路図や抵抗の値も、自分ごととして理解できるようになりました。
教材やYouTube動画でも簡単に体験できるので、まずは小さな電子工作から始めてみるのがおすすめです。
③ マンガや動画で学んだとき「わかる」に変わった
漫画や動画を使って、視覚的・物語的に学ぶと、抽象的な理論もぐっと身近に感じられます。
難しい数式も、ストーリーがあればスッと頭に入ります。
たとえば『はたらく細胞』が生物を楽しくしたように、『でんじろう先生の実験動画』や『マンガでわかる電気回路』などを活用すると、学びが楽しくなります。
僕自身も受験期に電気漫画を読み、「あ、そういうことか」と腑に落ちる経験が何度もありました。
「楽しい」を入り口にすれば、自然と深く学びたくなります。
✍️ まとめ|電気は“つながる”と楽しくなる!
電気がつまらないと感じるのは、「現実とのつながりが見えない」から。
でも実は、電気はあなたの身の回りすべてと関係している分野です。
- スマホが動く仕組み
- スイッチ1つで電球が光る原理
- ゲームコントローラや冷蔵庫の頭脳
こういった「日常」に目を向けるだけで、電気はグッと面白くなります。
そして、ほんの少しの工夫で、あなたにもその面白さは体験できます。

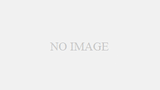
コメント